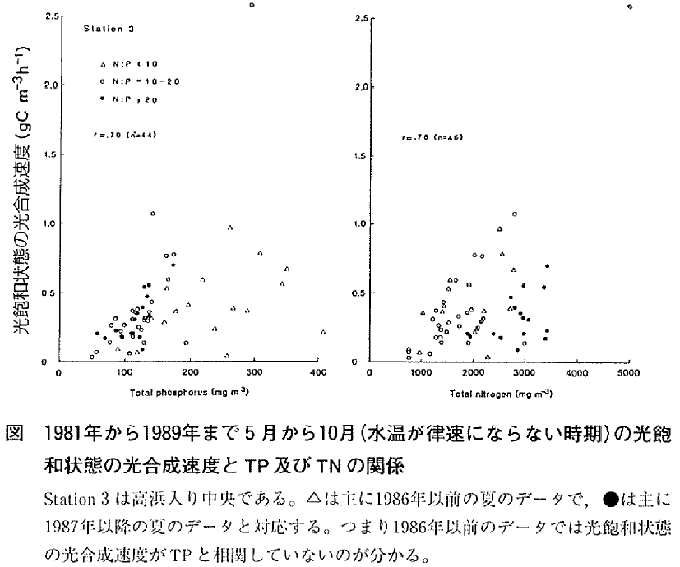「霞ヶ浦は変わった」
経常研究の紹介
高村 典子
国立公害研究所ニュースVol.6,No.5(1987年)に掲載された座談会「霞ヶ浦は変わったか」を覚えている方は少ないかもしれない。霞ヶ浦ではミクロキスティス(Microcystis)を優占属とするアオコの大発生が1970年の初めのころから毎年夏に起こり、様々な環境問題を引き起こした。ところが、1987年の夏、そのアオコが突然姿を消した。当時の座談会では、一過性の現象なのか、今後も続く現象なのかを今後注意深く観測する必要があると締めくくられている。霞ヶ浦の全域調査はその後も月1回の頻度で行われ相崎、海老瀬、福島、細見、岩熊、高村、花里、河合、野尻、稲葉、小沢らのメンバーで湖に出ている。私は植物プランクトン種の細胞数の計測と光合成量(基礎生産量)の測定を行っているが、1987年以降ミクロキスティスの量は極端に減り、変わって、やはりラン藻のユレモ(Oscillatoria属)が多く観察されるようになった。ユレモもアオコの原因種の一つであるが、糸状性で群体を形成せずミクロキスティスほどガス胞が発達していないため表層で粉をふいたようにならない。
変化の前後9年のデータを眺めて見ると、夏の植物プランクトン種の変化は湖水の夏のTN(全窒素量)/TP(全リン量)比の変化と対応することが分かった。つまり、ミクロキスティスが大発生した1986年以前では夏のTN/TP比の最小値は5.0-8.0であったのに、1987年以降は 16.0-17.1となった。さらに、5月から10月までの、光強度が律速しない植物プランクトンの光合成速度は1986年以前は窒素制限であったにもかかわらず、1987年以降はリン制限へ変化していることが分かった(図)。海老瀬氏によると霞ヶ浦流域からの窒素リンの負荷量は雨量に依存するが、晴天時では近年無リン洗剤の普及などでリンの流入負荷が横ばい、もしくはわずかばかり減少しているが窒素の負荷は年々増えているということである。おそらくこれが反映されて、さらに、夏期の植物プランクトン種が変わったために(おそらくユレモはミクロキスティスほど底泥のリンを持ち上げる能力がないのではないかと考えている)、湖水中のTPが減少しTNは増加し、結果的にTN/TP比が上がったと考えられる。
N/P比(TN/TP比より広義)は優占種を決定する重要な要因の一つであると考えられている。1970年代、湖の富栄養化の研究が華やかなりし頃、カナダでは自然の池に様々な比率の窒素・リンを放り込んで実験を行った。その結果、N/P比(負荷量としての)が5-10以下であると窒素固定をするラン藻が、それ以上では緑藻やクリプト藻が優占したとの報告がある。また、連続培養実験で最適N/P比は種特異的であり、ミクロキスティスで4.1、ユレモで12.0との報告があり、確かにN/P比が上がるとミクロキスティスよりユレモが優勢になるようである。さらに、ミクロキスティスが大発生している湖水中では硝酸態窒素は検出されず溶存態リンが余剰になる傾向にあるが、ユレモが大発生する湖では硝酸態窒素が余剰傾向を示す。これらを考え合わせると、霞ヶ浦の夏の植物プランクトンの種組成の変化が湖水のTN/TP比の変化に対応して起こったと考えてもよいと思う。ただし、湖の生き物は相互に影響しあっており、高次の栄養段階の生き物の影響などは無視できない。反対に植物プランクトン種が変わったことで基礎生産量は落ち込んでおり、他の生き物にも影響がでているはずである。
本研究所の霞ヶ浦全域調査は17年目を迎えている。参加研究者が増えデータが充実してきたのは4〜5年目くらいからであったろうか。長期にわたる湖の定期調査を行っているのは日本では信州大学の臨湖実験所の諏訪湖1定点と京都大学大津臨湖実験所(現生態学研究センター)の琵琶湖2定点(北湖南湖各1定点)だけである。これほど多くの、様々な専門分野の研究者が参加して行っているのは唯一霞ヶ浦だけであろう。湖を利用し湖と共存するには湖を知ることが大切である。琵琶湖に次いで日本第2の面積を持つ霞ヶ浦も、日本の高度成長期の1960年代には全くデータのない空白の10年がある。実にこの間にこそ著しい変化が起こっていたのである。
目次
- Global, International, National そして Local巻頭言
- 国立環境研究所のこれから論評
- 小泉明前所長紫綬褒章を受賞その他の報告
- 湾岸戦争に伴う環境破壊プロジェクト研究の紹介
- 湿原の環境変化に伴う生物群集の変遷と生態系の安定化維持機構に関する研究プロジェクト研究の紹介
- 培養細胞を用いた大気浮遊粉じんの毒性評価手法経常研究の紹介
- '91IGAC/APARE/PEACAMPOT航空機観測について研究ノート
- 波照間−地球環境モニタリングステーション竣工記念式典報告その他の報告
- 地域環境特別研究発表会報告その他の報告
- 環境月間特別講演会報告その他の報告
- 主要人事異動
- 編集後記