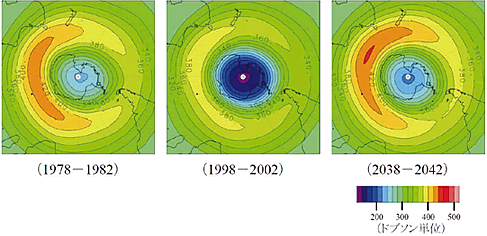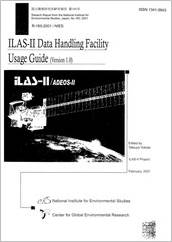成層圏オゾン層変動のモニタリングと機構解明プロジェクト(終了報告)
平成13〜17年度
国立環境研究所特別研究報告 SR-70-2006
1 研究の背景と目的
国際的なオゾン層保護の取り組み(オゾン層破壊物質であるフロン・ハロン類に対する規制)の効果は、1990年代後半にはオゾン層が存在する成層圏においても塩素・臭素濃度が減少傾向に転じるに至った、と言う形で現れてきた。一方で、今後オゾン層がフロン・ハロン濃度の減少に呼応して回復に向かうと言う確固たる証拠は得られていない。そこで本研究プロジェクトでは,人工衛星ならびに地上からのオゾン層の監視、監視・観測データを活用したオゾン層変動機構の解明、ならびに成層圏数値モデルの開発とオゾン層の将来変動の予測を行い、オゾン層保護対策の効果の検証と今後のオゾン層保護の取組みのための科学的知見を得ることを目的とした。
2 報告書の要旨
本プロジェクトはサブテーマを設定していないものの、オゾン層の監視、オゾン層変動機構解明、オゾン層のモデル化を3本の柱としてプロジェクトを進めた。以下に本プロジェクトの主な成果をまとめた。
『オゾン層の監視』-衛星からの極域オゾン層の監視-
人工衛星に搭載された成層圏監視センサー「改良型大気周縁赤外分光計(ILAS)」及びILAS-II(それぞれ「みどり」、「みどりII」衛星に搭載)によって取得された極域オゾン層のスペクトルデータの処理(化学種ごとの高度分布情報の抽出)、データ検証、ならびにオゾン層研究者への検証済みデータセットの提供を行った。
ILASおよびILAS-II観測では、人工衛星の不具合の結果、共に1年に満たない限定的な期間の観測を余儀なくされた(ILAS: 1996年11月~1997年6月の約8ヶ月間。ILAS-II:2003年4月~10月の約7ヶ月間)。しかし幸いな事に、ILASでは大規模なオゾン層破壊が起こった北極域を、またILAS-IIでは当時最大規模に発達した南極オゾンホールを捉えることが出来た。
ILAS観測データは検証解析を終えバージョン6.0データとして一般研究者向けに提供を行った。提供データはオゾン(O3)、硝酸(HNO3)、二酸化窒素(NO2)、亜酸化窒素(N2O)、メタン(CH4)、水蒸気(H2O)、硝酸塩素(ClONO2)の7化学種と可視波長でのエアロゾル消散係数(AEC)である。また検証解析の主な結果は、アメリカ地球物理連合の学術誌「Journal of Geophysical Research(以後 J. Geophys. Res.と略す)の特集号として発表された(2002)。
ILAS-II観測データについても検証解析を終え、バージョン1.4データとして提供をおこなっている。提供データはオゾン(南半球の検証解析結果を図1に示す)、硝酸、亜酸化窒素、メタンとエアロゾル消散係数である。検証解析の主な結果は、ILASと同様に、J. Geophys. Res.に特集号として発表された(2006)。
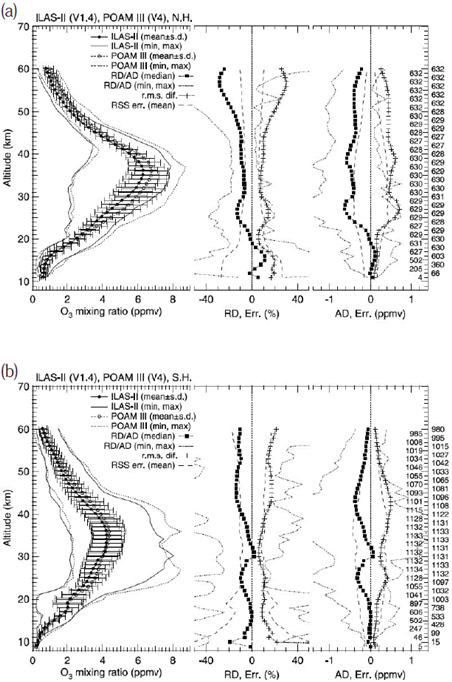
-地上からの日本上空オゾン層の監視-
地上からの日本上空オゾン層の監視として、つくば(国立環境研究所内)において1988年よりオゾンライダーによる、また1996年からはミリ波オゾン分光計を用いた観測を行っている。また北海道陸別町においてもミリ波オゾン分光計による観測を1999年12月より継続している。地上観測は国際的な観測ネットワークであるNDSC(Network for the Detection of Stratospheric Change)との連携のもとで実施され、検証済みのデータはNDSCデータベースに提供された(つくばオゾンライダー)。
オゾン層監視手法の改良にも取り組み、ミリ波オゾン分光計の広帯域化とデータ質の向上を図り、現在では、成層圏から中間圏に及ぶ14~76kmの高度領域でオゾンの連続モニタリングが可能となっている。
『オゾン層破壊の機構解明』-極域でのオゾン層破壊-
ILAS/ILAS-II観測データの活用による極域オゾン層破壊に係わる機構解明が進んだ。特に、大規模なオゾン層破壊が起こった1996/97年春季の北極オゾン層破壊において、南極オゾンホールで提唱されている「極渦の強化→極域成層圏雲(PSC)生成→PSC上での不均一反応による塩素の活性化と脱窒・脱水→大きなオゾン分解速度」の機構が北極域においても働いている事を実証した。
北極域でPSC生成とその重力落下による脱窒過程の進行を捉えた例として、北極渦内での各高度に分配された硝酸量(ΔHNO3)の鉛直分布を図2に示す。17~21kmの高度域でのガス状硝酸の減少量が、高度15km以下の領域での観測されたガス状硝酸の増加量と一致している事や、周囲の気温とPSC発生の閾値温度との関係から、「PSCへの硝酸の取り込み⇒PSC粒子の重力落下⇒PSC粒子からの硝酸の蒸発」が起こったとして解釈される。
[注:ΔHNO3について:PSCによるガス状硝酸の除去(脱窒)が無い時に見込まれるガス状硝酸量と観測された硝酸量の差。負のΔHNO3はガス状硝酸濃度の減少がある事(脱窒が起こった事)に対応し、逆に正のΔHNO3はガス状硝酸濃度の増加がある事(硝化が起こった事)に対応している。]
また南極オゾンホール生成に関しても、PSCの生成やPSCによる硝酸の取り込み、オゾンホール内への上層大気からの物質輸送、オゾンホール内でのオゾン分解速度決定など、オゾンホール内での現象の定量的解明が進んだ。
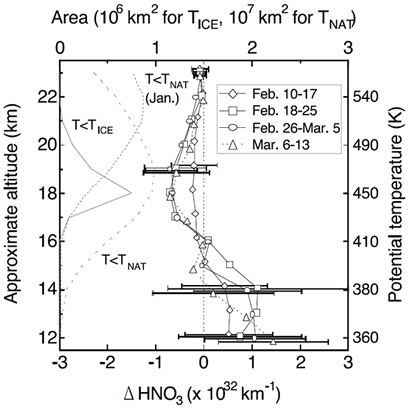
ILASおよびILAS-IIは高頻度で北極ならびに南極成層圏を観測した。その利点を活かし、異なった2つの日(例えば3/1と3/5)に同じ空気塊が観測できたケースを拾い出して、両者を比較する事で、その期間に注目した空気塊の中で化学的なオゾン破壊がどの程度進行したかを定量化した(MATCH手法の応用)。これはMATCH手法を衛星観測に応用した例であり、1997年春季の北極域でのオゾン層破壊におけるオゾン分解速度が最大で1日当り80ppbvとオゾンホールに匹敵する値である事がわかった(図3を参照)。
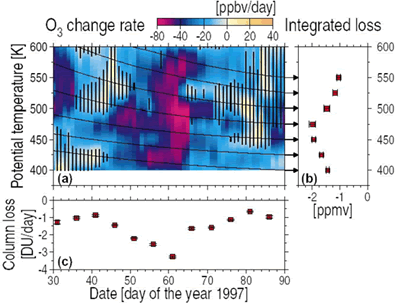
-中緯度オゾンの変動-
中緯度域でのオゾン変動は、極域でのオゾン層破壊の影響、中緯度でのオゾン分解、低緯度からの低オゾン濃度の空気の輸送、が複雑に絡み合って引き起こされている。特に極域オゾン層破壊の影響に関しては、極渦内の独特な化学反応によってオゾン破壊が進行した空気塊が極渦内外との空気の混合過程によって、極渦の外の大気に影響を及ぼすものである。本研究課題では、その影響を定量化する手法(時間閾値解析法と化学輸送モデルを併用する手法)を開発した。
つくばでのミリ波オゾン分光計を用いた上部成層圏から中間圏(高度38~76km)のオゾン濃度鉛直分布の長期連続観測データには、特徴的な季節変動が観測された。特に中間圏の高度56 km~68 km及び68 km~76 kmでは、それぞれで互いに位相の反転した半年周期変動が観測された(図4を参照)。中間圏でこの様な明瞭な半年周期のオゾン変動が観測された例は無い。現時点では観測されたオゾン変動を合理的に説明できる変動機構は提案されておらず、中層大気でのオゾン変動ならびにそれに関連する化学・輸送・波動プロセスに対する新たな問題提起となった。
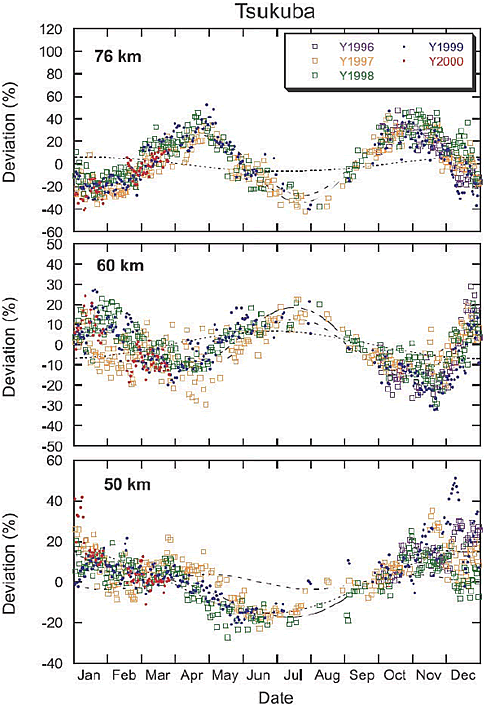
『オゾン層のモデリングと将来変動予測』
同一の大気大循環モデルをベースに成層圏オゾン層を取り扱う2つの数値モデル(化学気候モデルと化学輸送モデル)を本プロジェクト内において確立できた。観測された気象場を利用し、力学プロセスと化学プロセスを分離した議論を可能にした化学輸送モデルにより、極域オゾン層破壊と中緯度オゾン変動の関連などが明らかになった。また、成層圏での化学-放射—力学過程間の相互作用を取り込んだ化学気候モデルの開発・改良は、オゾン層の将来変動予測に向けた長期発展実験の実施を可能にした。数値実験の結果は、オゾン科学アセスメントにおいて引用された。
化学気候モデルを用いた南極オゾンホールの変化予測の数値実験(図5を参照)からは、オゾンホールは2000年-2010年頃に最大規模に発達するが、2020年ごろには縮小傾向に転じた事が認められる状況になると予想される。2040年ごろにはオゾンホールはかなり縮小し、21世紀半ば過ぎにはオゾンホール現象は殆ど観測されなくなるものと予想される。