化学物質の生態影響評価のためのバイオモニタリング手法の開発に関する研究
平成7〜9年度
国立環境研究所特別研究報告 SR-29-'99
1.はじめに
化学物質の環境リスク評価は、化学物質の生物に対する毒性と暴露濃度との比較で行われる。近年の環境ホルモン問題を契機に、化学物質による環境汚染の実態が明らかにされつつあり(暴露量)、化学物質の水生生物に対する毒性評価(毒性)とそれらに基づいた生態系への影響評価の必要性が一層高まってきた。化学物質の毒性値は特定の試験生物を用い、OECDなどのテストガイドラインに準拠した生物試験で求められる。これに則って国際的な共同作業(HPV Project;高生産性化学物質プロジェクト)として、多数の化学物質の毒性の一次評価が進行中である。一方、暴露濃度は化学物質の生産量・移動量の把握、非意図的に生成される量の推定結果から把握(PRTR法)されようとしている。これらの試みから化学物質毎の環境影響リスク値が算出されより有効な化学物質の管理が可能となる。一方、実際の野外環境は多種多様な化学物質で同時に汚染されその濃度も変動しており、それらの影響は単独の物質の毒性値から推定することは困難な場合が多い。そこで化学物質の生態影響評価にはこれとは別途、総合的な化学物質のリスク評価手法が必要とされる。その1つが生物を用いて汚染の程度を測る生物検定であるが、さらに一歩進めて化学物質の影響を常時監視して評価するバイオモニタリング手法が有効と考えられる。
本研究は(1)生態影響評価のためのアッセイ手法を再構築し、(2)バイオモニタリングに適する生物種を見いだし、既存の手法に応用すること、(3)独自の発想で新たな手法の開発を行うことを目指したが、これらの目的を達するために、桜川(霞ヶ浦流入・最大河川)の河川水を連続的に汲み上げて試験する施設を整備し、実際の河川環境に即したバイオモニタリング手法の開発を指向した。
2.研究概要
(1) 早期警戒的なバイオモニタリング手法の開発
有害物質の河川への流出事故や農薬の流入など、比較的急速な濃度変化に敏速に対処するため、常時リアルタイムで生物反応を監視し環境リスクをバイオモニタリングする手法である。応用面では、生物反応がある閾値を越えた場合、信号を発し自動採水(化学分析用)する一方、警報をもとに迅速な対策を執ることが出来る。実用化のためにはメンテナンスが容易で、省力化のため自動化できること、さらに生態影響を反映することが求められる。
1)ヌカエビの行動を用いた手法で高感度のモニタリングが可能(図1)
ヌカエビは、特に殺虫剤汚染に関しては魚類より桁違いに高い感受性を有し死亡に至らない濃度でもその行動が変化した。この行動変化を自動的に画像解析装置で捉えることができ、農薬類の汚染をリアルタイムで監視するシステムを開発した。
2)マシジミの水管伸縮も有効な指標となる(図2)
マシジミは平地の河川・湖に生息し環境が悪化すると水管を縮め貝殻を閉じてしまう。この反応は非常に敏速で、簡易で安定な手法として開発した。
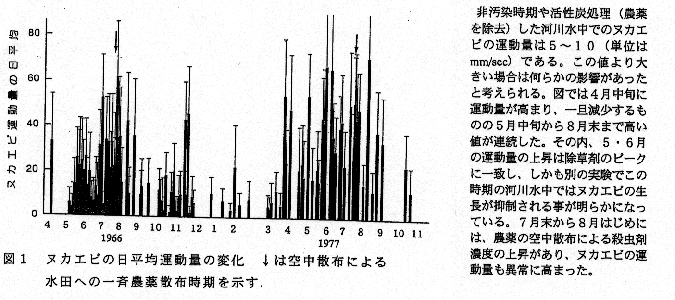
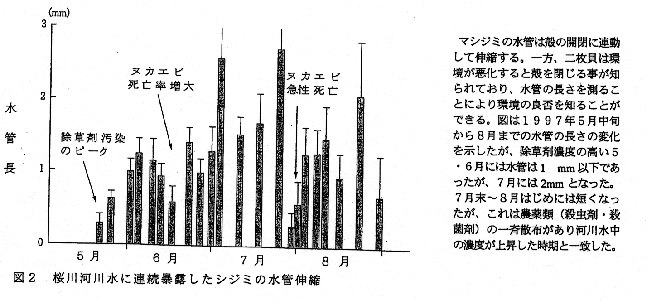
(2) 慢性的な影響評価のバイオモニタリング手法の開発
生長や繁殖に及ぼす影響は、環境水に連続的に暴露してはじめて現れる。特に、内分泌撹乱物質などの影響評価には試験生物をコントロール(光・温度など)した状態で、環境水に連続的に暴露し、繁殖への影響を見る必要があり、バイオモニタリング施設を用いた各種実験を試みた。
1)水草類の生長は水中の除草剤濃度で大きく変動(図3、図4)
一次生産者への影響評価手法としてウキクサ等の水草類を用いた手法を開発した。流水式水槽(水温制御・連続照明下)でウキクサを河川水に暴露しその生長を葉面積の増加量(図3)で把握することで高感度で水中の農薬(除草剤:図4)の影響を監視することが可能であった。
2)ヌカエビの長期暴露モニタリング(図5)
ヌカエビは水中化学物質の影響で行動の変化が見られるほか、急性的な影響として死亡率の上昇、慢性的な影響として生長や繁殖への影響が見られる。特に環境水への連続暴露により、採水サンプルを用いた試験では見過ごす様な毒性の変動を観察することが出来た。河川水中の毒性物質により、継続的な運動量の増加(エネルギー消耗)を受けたヌカエビは、対照(活性炭ろ過・河川水)に比較し、生長阻害を受けることを明らかにした。
3)二枚貝の生長は水中及び懸濁粒子や底質の化学物質を反映
淡水産二枚貝であるドブガイとマシジミの生長速度を連続的に測定すると、その値は季節的に大きく変動した。この変動は暴露した河川水の水温と水中の餌濃度(クロロフィルa)の2要因に依存していたが、他に農薬濃度が高い時期に著しく生長が抑制されることが分かった。そこで水温と餌濃度と生長との関係をモデル化した。次に推定生長速度を算出し実測生長速度と比較した(図6)。結果は除草剤濃度の高まる春から初夏および農薬の空中散布があった時期にその差が顕著となり著しい生長阻害が起こっていることを示した。二枚貝は水中、懸濁粒子および底質の間隙水中の化学物質と全ての経路から化学物質の総合的な影響を受ける可能性があり、しかも給餌の必要がなく、増水時の濁水にも安定して生存するため、年間を通した長期のバイオモニタリングに適した材料であることが分かった。
4)小型淡水魚に対する河川水暴露、雄の受精能に影響
ゼブラフィッシュを河川水に長期間暴露し、定期的に雌雄のペアを作り産卵とふ化率の変動を観察した。その結果、河川水に暴露した雄を親とする卵のふ化率が特異的に低下した。同じように暴露した雌個体では影響が見られず、河川水中に雄の受精能を低下させる化学物質が存在することが示唆された。
5)魚体中の化学分析モニタリング
河川で魚類を採取し、筋肉中の農薬類濃度を測定した。農薬の種類によっては、長期間存在したり、農薬の散布後に急速に吸収されその後速やかに排出されるものなど様々な挙動が見られた。これらのデータは水中の農薬濃度や他の試験生物の反応と併せて生態影響を評価する有効なデータとなった。
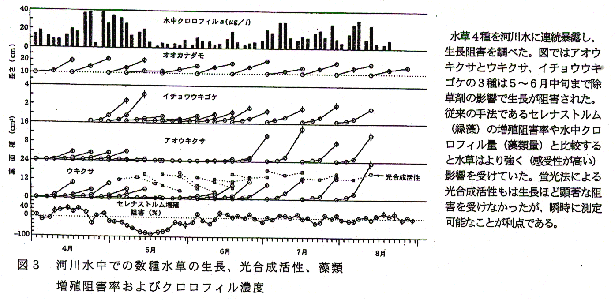
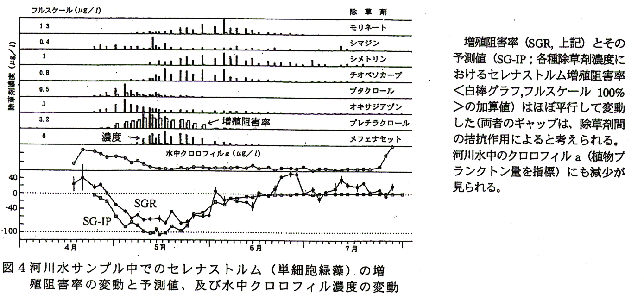
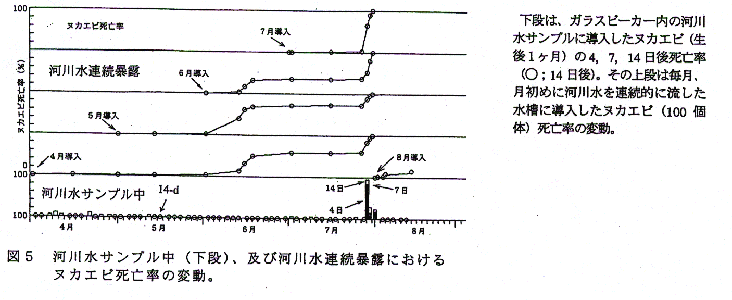
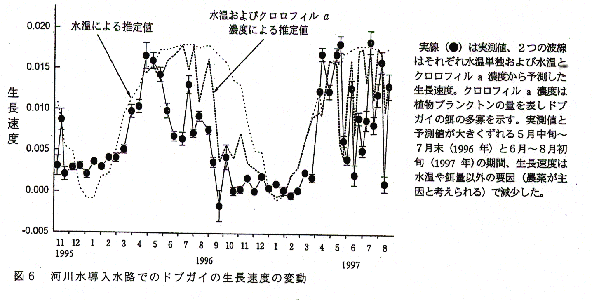
(3) 生物試験と生物調査結果に基づく生態影響評価
試験生物によっては、環境水への連続暴露試験がほとんど不可能であるか、その実施のためには大がかりな試験系を開発する必要がある。このような制約以外にも、化学物質の河川全体への影響評価などに、広域的なバイオモニタリング手法が求められる。試験生物として、これまで国立環境研究所アクアトロンで継代飼育している水生生物から数種を選択した。環境水や汚染底質に対する生物試験と関連する生物調査の結果から、化学物質の生態影響評価を行った。
1)藻類群集の耐性の獲得過程から化学物質(除草剤)の影響を評価
数種の除草剤に関し、除草剤汚染程度の異なる環境(実験水田・河川)から多数の藻類種を分離培養し、耐性試験を行った。珪藻類は概して耐性があり、緑藻類は比較的高い感受性を示した。そのため、除草剤の影響が強い場合、緑藻ではそれまで抑制されていた薬剤耐性種、あるいは耐性系統が感受性系統と置換して顕著になる。このような耐性獲得の推移を明らかにし、除草剤汚染の状況をある程度推定可能であることを示した。珪藻・藍藻は概して耐性があったが、河川に優占する種類が多く、適当な種を選択し、生物試験に備えることは必要である。
2)一次消費者としてミジンコ類を用いた繁殖影響試験
カブトミジンコ(D.galeata)、ミジンコ(D.pulex)を用いて河川水の14日間繁殖試験を実施した。河川水をろ過(ガラスフィルター)し、懸濁粒子や植物プランクトンを除去し、餌としての決まった量のクロレラを与え、死亡・産仔数を記録した。ミジンコ類においても産仔前に死亡が起こったり、産仔数が減少するなど様々な影響が観察された。
3)汚染物質の影響を広域で調査
田園地帯を流下する小貝川(全長110km)の94kmの区間に16定点を定め、6、7、8月に河川水を採取して、ヌカエビ、ヨコエビを用いた14日間生物試験を実施した。6月に採集した河川水では、河川水が増水していたにも拘わらず、ヨコエビに対する毒性は上流から下流まで高い値を示した。また、8月の河川水では上流側の4地点のみ、両種ともに著しい毒性を示すなど河川の毒性は広域的にもダイナミックに変動し、感受性の高い水生生物には致死的であり、生態系に影響を与えていることを明らかにした。
4)ヌカエビに対する毒性と河川生物相の相関
5月から8月までヌカエビに対して著しい毒性が検出された河川において、生物調査を実施し毒性との関係を明らかにした。毒性が著しい地点で採集された生物は、コガタシマトビケラをはじめ、殺虫剤に耐性を有す種がほとんどであった。捕食者のヘビトンボも薬剤耐性を示す種であるが、高い毒性が続く時期には生息せず、餌となる水生昆虫の減少がその原因と考えられた。
5)我が国の環境にふさわしい底質試験法の検討
水中の化学物質の多くは最終的に底質に沈降するため、底質試験が必須であるが、国内では実績がほとんどない。OECDでもユスリカを用いた底質試験法ガイドラインの制定を急いでいるが、本研究で見いだしたセスジユスリカ(在来種)感受性系統を試験生物の1つに加えることをガイドライン検討委員会に提案したところ、検討リストに加えられることとなった。在来種が認められることで我が国の環境にあった種を用いて国際的に通用する試験を行うことが可能となった。本種を用いて殺虫剤(エトフェンプロックス)で汚染された河川底質を暴露すると、汚染底質の影響で急性致死が観察された。ヌカエビでも同様なことが認められた。
6)化学物質の生殖異常に係る生体影響評価の検討
海産巻貝のイボニシで明らかにされている生殖異常について、化学物質の生態影響評価にインポセックス率・輸卵管閉塞率が有効であることを示唆した。
3.本研究のまとめと今後の課題
(1)バイオモニタリング施設を利用し、試験生物を河川水、または水路に沈着した底質に長期・連続的に暴露した結果、採水・採泥サンプルでは評価出来ない様々な生態影響のプロセスが明らかとなり有効な手法であることを示した。
(2)バイオモニタリング施設での監視、採水・採泥サンプルへの試験生物の暴露、藻類の耐性系統の出現、これらの結果に基づく生物影響調査など総ての結果は化学物質、なかでも農薬類の潜在的な生態影響が現在も様々な局面で存在し、生態系に影響し続けていることを明らかにした。
(3)内分泌攪乱物質の魚に対する繁殖影響を示唆する結果も得られたが、今後さらにこの問題を詳細に研究するには、バイモニタリング施設の給水系(特に、配管等)の材質を、内分泌攪乱物質を溶出するおそれのない材質に変更するなどさらなる検討が必要とされる。
(4)今回のバイオモニタリング施設を利用した結果は一つのモデルケースである。バイオモニタリング施設(自動化など)を要所に設置し、化学物質による環境リスクを連続的に監視しできるよう、更に手法を充実させる必要がある。
国立環境研究所
生物圏環境部
上席研究官 畠山成久
(Tel 0298-50-2503)
用語説明
-
バイオモニタリング(特に化学物質の生態影響評価においての)生物が有害化学物質に暴露された場合、致死以外にも各種の生物反応を示す。水生生物では例えば生長阻害、忌避行動、防衛反応、繁殖阻害、酵素阻害反応などさまざまである。このような生物反応を、経時あるいは連続的(観察頻度は生物種や測定項目によって様々であるが)に観測して、生態系に及ぼすリスク評価を行う。
-
流水式暴露汚染物質を含む流水を水槽あるいは水路中に確保し、その中で試験生物を生育させることにより、汚染物質に曝露させること。ここでは桜川沿岸にバイオモニタリング施設を設置した。
-
ヌカエビ淡水産の小型エビで、実験生物化され各種実験に用いている。かっては東日本の小河川や池沼に豊富に生息し、日本人の重要な蛋白源になっていたが、現在では化学物質等の汚染が無いごく限られた水環境に生息している。
















