21世紀に向けて,我々は聡くあらねばならぬ
鷲田 伸明
ニーチェはその遺稿の中で「自分の死後100年間はニヒリズムの時代で,次の100年間は本格的なニヒリズムの時代になる」と予言していたと言われている。ニーチェは1900年に没しているから,21世紀が正に彼の言う本格的ニヒリズムの時代に相当する。ニヒリズムあるいはニヒリストという言葉が文学に初めて登場したのは,1862年に発表されたツルゲーネフの「父と子」に登場する青年バザーロフが最初であると言われている。この小説の中で医者であり化学者であるバザーロフは,古い道徳,宗教の一切を否定し,それらの破壊を建設の第一歩とする急進的インテリゲンチャとして,迫力ある青年像で描かれている(多少,著者の皮肉も見え隠れしているが)。「神は死んだ」—皆が寄ってたかって殺したのだ—と言った哲学者は,信仰を捨て科学技術に走るであろうこの先2世紀の人類の姿をも見ていた。
21世紀を目前にして我々は今後益々破壊と建設を進行させていくことになるのだろうか。強い競争力を建前とした独立行政法人化などは軽いもので,科学の片方は宇宙ステーションから火星移住計画に走り,もう片方のバイオテクノロジーは原爆開発前夜の様相を呈している。かつて神が作り給うた原子核など壊してよいのかと恐れつつ,人は核分裂からエネルギーを取り出したのと同様に,今や神が作り給うた遺伝子をバラバラにしたり,人工合成したりしている。それに比べると地球を守れ,生態系を守れに代表される環境研究は単なる保守主義として,力敗けしないだろうか。いつまでもsustainable development(持続可能な発展)だけでは心もとなくはないだろうか。ここらで何か倫理的哲学が欲しいと思いつつも,あふれる情報に翻ろうされる大衆を尻目に,情報,宇宙,バイオ技術を集中的に手中に収めた者に権力が集中するのが21世紀なのかも知れない。
3年前に逝去された丸山眞男教授が東京大学法学部で行った講義録(全7冊)が東京大学出版会から最近出版されている。その第三冊に1960年度にただ一度だけ行われた「政治学」の講義内容が掲載されている。「政治は可能性の技術(Kunst des Möglichen)である」というビスマルクの言葉を命題とした講義内容は,政治または政治学を科学技術研究に置き換えても違和感を与えない普遍性の高い理念を我々に与えてくれる。その第二講に「政治的分析の諸方法」という講があり,価値充足度の高い(または低い)社会,前進的(または停滞的)社会の構造を下の四種のパターンで表している。ここでLはリベラル,Cは保守,RAは過激性(Radical),REAは反動(Reactionary)である。安定しつつ前進する社会はACの合体型でLが最大でREAが最小の社会(丸山は明治20年頃の日本を例にあげている)であり,安定しているが停滞している社会(例えば徳川体制)はAD型でCが最大でRAが最小の社会であるとしている。その他RAが最大でCが最小のBC型は不安定な革命型社会であり,REAが最大でLが最小のBD型社会は不安定な停滞型(例えばナチ体制)であると分類している。
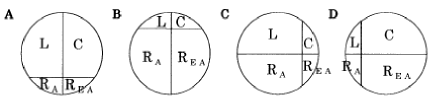
図B 価値充足度の低い社会(不安定)
図C 前進的・実験的社会
図D 停滞的社会
25年前(昭和49年)に研究員の平均年齢32~33歳でスタートした国立公害研究所(現国立環境研究所)は,その後8~9年間は安定した研究費と成長期にある研究員や研究テーマの下でAC型を維持できた。昭和59年頃から平成元年の組織見直し期にかけての6年間は予算の面では明らかに停滞型であったが,研究員のポテンシャリティー(潜在力)は十分に温存されていたと見てとれる。平成2年以後の予算の増大はBC型に近く,それに対して平均年齢43歳になった研究員の方は単に高齢化の問題だけでなく若い人達の保守性の問題もあって,なかなか自覚しにくいことではあるが,停滞型になりつつあることは否定できない。それにも増して心配なのは,知的ポテンシャリティーの枯渇であろう。予算面とそれを受ける研究員との間に良いバランスがあってはじめて,恐らく大多数の人が理想と考えるであろうAC型の研究社会を作れることは当然であるが,同時に,知的財産の食いつなぎや,食い潰しではない,前進的知性の獲得がなければAC型社会は作れない。
当研究所の現在の予算は昭和63年に比べ約3倍に増大し,それに伴いプロジェクトという名の研究の事業化が一層進行した。これは単に当研究所だけでなく世界的傾向であることを考えれば,本格的ニヒリズムという名の21世紀は研究よりも研究事業の時代になるであろうことを暗示している。独立行政法人化後の評価は研究事業体としての評価が大いに含まれることになるだろう。当研究所が昨年作成した中核的環境研究機関のヴィジョンにも事業性は色濃く描かれている。それでも研究と研究事業の区分を明確化し,賢く両立させることが我々の使命であろう。多分我々は「真理は人間の意志にかかわらず,真理の方から人間に近づき,人間を高いところに導いてくれる」という啓蒙時代の精神の光の輝きを知性の遺伝子の奥深くにまだ内蔵しているのだろうから。
要は我々はより賢くあらねばならない。面白いのは,このような時に我が国では若者の理工系離れと学力低下が深刻化していると言われていることである。最近,本屋で求めたR.ダンバーの「科学がきらわれる理由」によると,この問題はイギリスでも深刻化していることがわかる。この技術先進国共通の問題には21世紀の科学技術のあり方の姿が影を落としていると言えよう。それでもなお,21世紀の日本の,また世界の経済が科学技術に依存せざるを得ないことは間違いない。だからと言って我々は決して優遇される訳ではないことも知っておく必要がある。例えば徳川時代,日本の経済の8~9割は農業に依存していたが,農民が決して優遇されることはなかったのだから。


